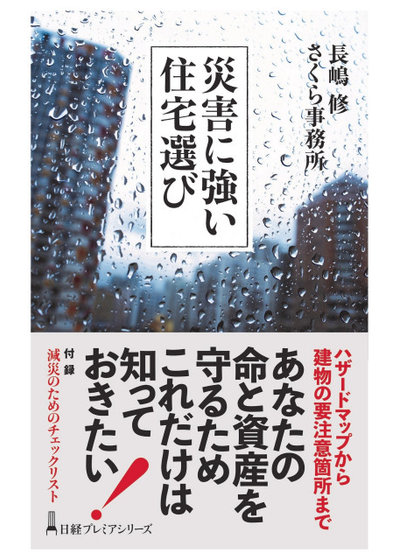コメント
災害に強い住まいづくりで知っておきたい基本ポイント
家づくりをする際には、地震だけではなく、水害リスクもふまえなくてはいけません。専門家ではない私たちが知っておくべきこととは?
Mamiko Nakano
2020年8月6日
editor-writer-translator
毎年のように起きている大雨や台風による災害。家づくりをする際には、地震のほかに、水害のリスクについても把握しておかなければいけない時代になってしまいました。
では、土地や建物の災害リスクについて、どのように知ったらよいのでしょうか?住宅と災害に関するセミナーなどを数多く主催している不動産コンサルティング会社「さくら事務所」の代表取締役社長・大西倫加さんに、基本的なポイントについて聞きました。
では、土地や建物の災害リスクについて、どのように知ったらよいのでしょうか?住宅と災害に関するセミナーなどを数多く主催している不動産コンサルティング会社「さくら事務所」の代表取締役社長・大西倫加さんに、基本的なポイントについて聞きました。
2018年、西日本豪雨の被害状況(写真提供:Peace Winds America)
1 住むことを検討している土地や街の情報を調べるための、基本的な方法を教えてください。
気になる土地や家があったら、まずはインターネットで閲覧できるハザードマップを確認しましょう。河川氾濫による洪水や地震の津波、土砂災害、火山噴火といった災害に関する被害を予測、被害範囲が地図上に示されています。
住みたいエリアの自然災害リスクをまとめて調べるには、国土交通省のハザードマップポータルサイトにある「重ねるハザードマップ」が便利です。
とはいえ、ハザードマップは全自治体の公開ではなく作成基準も異なり、万全ではありません。古地図で地歴(その土地の歴史)、「地理院地図」で土地の高低凹凸もあわせて確認しましょう。
1 住むことを検討している土地や街の情報を調べるための、基本的な方法を教えてください。
気になる土地や家があったら、まずはインターネットで閲覧できるハザードマップを確認しましょう。河川氾濫による洪水や地震の津波、土砂災害、火山噴火といった災害に関する被害を予測、被害範囲が地図上に示されています。
住みたいエリアの自然災害リスクをまとめて調べるには、国土交通省のハザードマップポータルサイトにある「重ねるハザードマップ」が便利です。
とはいえ、ハザードマップは全自治体の公開ではなく作成基準も異なり、万全ではありません。古地図で地歴(その土地の歴史)、「地理院地図」で土地の高低凹凸もあわせて確認しましょう。
ハザードマップポータルサイトのトップページ
2 マンションを選ぶ場合、まず最初にチェックしておきたいポイントを教えてください。
ドライエリアとは、建物の周辺を掘り下げて作った空間のことです。これがあることで日差しと風通しがよくなりますが、雨が流れ込みやすく、水害に遭いやすいという側面があることを知っておきましょう。
機械式駐車場の多くは、大雨に備えた排水設備を備えてはいるものの、近年の想定を超えるレベルのゲリラ豪雨には対応しきれないことも考えられます。スペースの限られた都市部のマンションでは難しいかもしれませんが、地上の平置き駐車場が、水害リスクの面では安心といえます。
2 マンションを選ぶ場合、まず最初にチェックしておきたいポイントを教えてください。
- 確認したい地下や半地下
ドライエリアとは、建物の周辺を掘り下げて作った空間のことです。これがあることで日差しと風通しがよくなりますが、雨が流れ込みやすく、水害に遭いやすいという側面があることを知っておきましょう。
機械式駐車場の多くは、大雨に備えた排水設備を備えてはいるものの、近年の想定を超えるレベルのゲリラ豪雨には対応しきれないことも考えられます。スペースの限られた都市部のマンションでは難しいかもしれませんが、地上の平置き駐車場が、水害リスクの面では安心といえます。
- 管理体制も把握しよう
高基礎で作られた一戸建て
3 一戸建てに住むことを考えた場合、まず最初にチェックしておきたいポイントを教えてください。
1981年の新耐震基準は1978年に起こった宮城県沖地震(最大震度5)をふまえ、最大震度6以上でも人命を損なうような「倒壊」をしないことを目指し制定された基準です。
その後、1995年の阪神・淡路大震災での木造住宅被害を受け、2000年に木造住宅の基準が強化され、接合部の金具取付や耐力壁の配置などが規定されました。また地盤に応じた適切な基礎をつくることも規定され、事実上、地盤調査が必須となりました。これを「新・新耐震基準」とか「2000年基準」などと呼んでおり、こちらの基準にあっているものを選ぶことをおすすめします。
また、住宅性能表示は「耐震等級3」取得ならかなり安心です。耐震等級3は基準法最低限レベルである等級1の1.5倍の耐震性能を前提として設計されています。
建築基準法「新耐震基準」である等級1は震度5レベルであればほぼ損壊しない、とはいえ震度6以上となると人命を損なうような「倒壊」をしないことを目指しており、損壊・大破しないわけではありません。つまり被害によっては、人命は助かるけれど大規模な補修や建て直しも必要になる可能性があるということです。
耐震性能3は消防署や警察署などの防災拠点と同等の耐震生になるので、小規模な補修で維持し、暮らし続けられる可能性が高くなります。また等級3を取得している住宅は地震保険の保険料が半額になるメリットもあります。
また、勾配がなく「陸屋根」と呼ばれる平らな屋根は、水が溜まりやすく屋根が傷みやすくなります。屋根が一方向だけ傾いている「片流れ屋根」も、雨どいへの負担がかかりやすく、雨漏りリスクが増大する懸念があります。取り入れたい場合にはこの点を理解し、設計・施工の担当者とよく相談した方がいいでしょう。
災害に備えるために。住まいについて知っておきたいこと
3 一戸建てに住むことを考えた場合、まず最初にチェックしておきたいポイントを教えてください。
- 耐震性能について
1981年の新耐震基準は1978年に起こった宮城県沖地震(最大震度5)をふまえ、最大震度6以上でも人命を損なうような「倒壊」をしないことを目指し制定された基準です。
その後、1995年の阪神・淡路大震災での木造住宅被害を受け、2000年に木造住宅の基準が強化され、接合部の金具取付や耐力壁の配置などが規定されました。また地盤に応じた適切な基礎をつくることも規定され、事実上、地盤調査が必須となりました。これを「新・新耐震基準」とか「2000年基準」などと呼んでおり、こちらの基準にあっているものを選ぶことをおすすめします。
また、住宅性能表示は「耐震等級3」取得ならかなり安心です。耐震等級3は基準法最低限レベルである等級1の1.5倍の耐震性能を前提として設計されています。
建築基準法「新耐震基準」である等級1は震度5レベルであればほぼ損壊しない、とはいえ震度6以上となると人命を損なうような「倒壊」をしないことを目指しており、損壊・大破しないわけではありません。つまり被害によっては、人命は助かるけれど大規模な補修や建て直しも必要になる可能性があるということです。
耐震性能3は消防署や警察署などの防災拠点と同等の耐震生になるので、小規模な補修で維持し、暮らし続けられる可能性が高くなります。また等級3を取得している住宅は地震保険の保険料が半額になるメリットもあります。
- 屋根の形と水災リスク
また、勾配がなく「陸屋根」と呼ばれる平らな屋根は、水が溜まりやすく屋根が傷みやすくなります。屋根が一方向だけ傾いている「片流れ屋根」も、雨どいへの負担がかかりやすく、雨漏りリスクが増大する懸念があります。取り入れたい場合にはこの点を理解し、設計・施工の担当者とよく相談した方がいいでしょう。
災害に備えるために。住まいについて知っておきたいこと
「災害に強い住宅選び」の書影
4 ハザードマップ(浸水リスク)説明が義務化されますが、それ以降でも注意すべきことはありますか?
8月末以降、不動産取引の重要事項説明の際にハザードマップ(浸水リスク)説明が義務化されることとなりました。
ただ、揺れやすさマップやハザードマップは250m四方程度の間隔で出されています。これは一般的なサイズの住宅でもおおよそ9軒ぶんくらいの広さで、自宅ピンポイントでの状況はわかりらず、付近の傾向を把握するにとどまります。
また、下水道や排水路から雨水が溢れて水浸しになる「内水氾濫」などについては分からない、といった盲点もあります。
一般的な説明だけでは分かりづらい点については、建築士や防災・地盤などの専門家に相談してみるのもいいでしょう。
大西さんが代表を務めるさくら事務所では、今年5月、住まいと水災リスクにフォーカスした「災害に強い住宅選び」(長嶋修/さくら事務所著、日本経済新聞出版)を発表。こちらの本には、これから家づくりをする人が知っておきたいポイントが、さらに詳しく記されています。
Houzzで住まいの専門家を探す
防災の記事をもっと読む
4 ハザードマップ(浸水リスク)説明が義務化されますが、それ以降でも注意すべきことはありますか?
8月末以降、不動産取引の重要事項説明の際にハザードマップ(浸水リスク)説明が義務化されることとなりました。
ただ、揺れやすさマップやハザードマップは250m四方程度の間隔で出されています。これは一般的なサイズの住宅でもおおよそ9軒ぶんくらいの広さで、自宅ピンポイントでの状況はわかりらず、付近の傾向を把握するにとどまります。
また、下水道や排水路から雨水が溢れて水浸しになる「内水氾濫」などについては分からない、といった盲点もあります。
一般的な説明だけでは分かりづらい点については、建築士や防災・地盤などの専門家に相談してみるのもいいでしょう。
大西さんが代表を務めるさくら事務所では、今年5月、住まいと水災リスクにフォーカスした「災害に強い住宅選び」(長嶋修/さくら事務所著、日本経済新聞出版)を発表。こちらの本には、これから家づくりをする人が知っておきたいポイントが、さらに詳しく記されています。
Houzzで住まいの専門家を探す
防災の記事をもっと読む
おすすめの記事
リフォーム・リノベーションのヒント
木造住宅の耐震リフォームの際に知っておきたいこと
文/中西ヒロツグ
耐震性の確保は、安全な住まいのために不可欠です。自宅の耐震補強のリフォームを考えた時に踏まえておきたいポイントをご説明します。
続きを読む
家づくりのヒント
災害に備えるために。住まいについて知っておきたいこと
文/志田茂
いざという時に冷静な判断をするためには、家が建っている土地や地域、家のメンテナンスの必要性などについて知っておくことが重要です。基本としてふまえておきたいことをお伝えします。
続きを読む
片付け
片付け収納の観点から考える防災対策とは
文/新倉暁子
大きな災害が起こり、今、できることは何だろう? と誰もが考えていると思います。そのひとつとして、住まいの防災対策についてぜひもう一度おさらいをしてください。
続きを読む
ニュース
西日本豪雨から1年。「板倉構法」の仮設住宅が示す可能性
昨年7月、西日本豪雨で被災した岡山県に、東日本大震災の被災地から木造の応急仮設住宅が移設されました。「板倉構法」だったからこそ、迅速な再利用が可能になったようです。
続きを読む